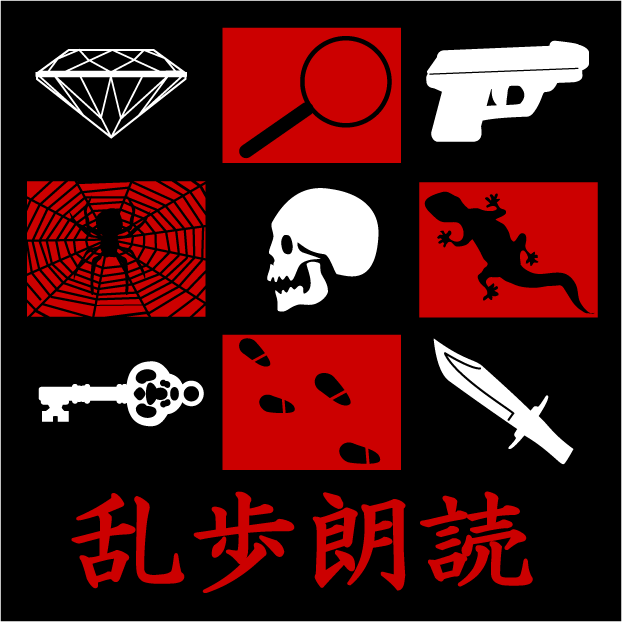top of page
ある夕方、千代田区の大きなやしきばかりのさびしい町を、ふたりの学生服の少年が、歩いていました。大きいほうの十四、五歳の少年は、名探偵明智小五郎の少年助手として、また、少年探偵団の団長として、よく知られている小林芳雄君でした。もうひとりの少年は、少年探偵団の団員で、小学校六年生の野呂一平君という、おどけものの、おもしろい少年です。
「なにか、すばらしい事件がおこらないかなあ。怪人二十面相も、ひさしくあらわれないし、ぼく、このうでが鳴ってしかたがないよ」
ノロちゃんは、うでをさすりながら、いいました。ノロちゃんというのは、野呂一平君の愛称なのです。
「バカだなあ、世間の人が、こわがって、さわぐのが、きみはすきなのかい」
小林団長にたしなめられて、ノロちゃんはペロッと舌を出して、あたまをかきました。
すると、そのとき、むこうの町かどから、ヒョイと、ふしぎなものがあらわれました。ロボットです。鉄でできた、ぶきみなかたちの人造人間です。そいつが、かくばったあたまをふりながら、かくばった足で、ギリギリと、歯車のおとをさせながら、むこうのほうへ歩いていくのです。
おもいもよらぬところに、人造人間があらわれたのを見ると、ふたりはギョッとして、たちすくんでしまいました。
朗読はこちらから!
bottom of page