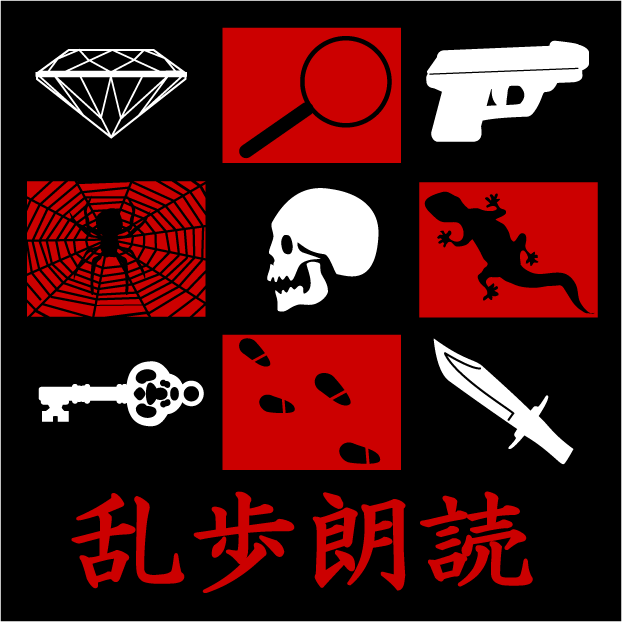top of page
「少年倶楽部」大日本雄辯會講談社、1936(昭和11)年1月号~12月号
第(3)章「人か魔か」より
小函の蓋が開かれますと、目もくらむような虹の色がひらめきました。大豆程もある、実に見事な金剛石が六顆、黒天鵞絨の台座の上に、輝いていたのです。
壮一君が十分観賞するのを待って、小函の蓋がとじられました。
「この函はここへ置くことにしよう。金庫なんかよりは、お前とわしと、四つの目で睨んでいる方が確かだからね」
「エエ、その方がいいでしょう」
二人はもう、話すこともなくなって、小函をのせたテーブルを中に、じっと顔を見合わせていました。
時々思い出したように、風が窓のガラス戸を、コトコトいわせて吹き過ぎます。どこか遠くの方から、激しく鳴き立てる犬の声が聞えて来ます。
「幾時だね」
壮太郎氏の時間を訊ねる回数が、だんだん頻繁になって来るのです。
「あと四分です」
二人は目と目を見合わせました。秒を刻む音が怖いようでした。
三分、二分、一分、ジリジリとその時が迫って来ます。二十面相はもう塀を乗り越えたかも知れません。今頃は廊下を歩いているかも知れません。……イヤ、もうドアの外へ来て、じっと耳を澄ましているのかも知れません。
アア、今にも、今にも、恐ろしい音を立ててドアが破壊されるのではないでしょうか。
「お父さん、どうかなすったのですか」
「イヤ、イヤ、何でもない。わしは二十面相なんかに負けやしない」
そうはいうものの、壮太郎氏はもう真青になって、両手で額を押さえているのです。三十秒、二十秒、十秒と、二人の心臓の鼓動を合わせて、息詰まるような恐ろしい秒時が、過ぎ去って行きました。
「オイ、時間は?」
壮太郎氏のうめくような声が訊ねます。
朗読はこちらから!
bottom of page