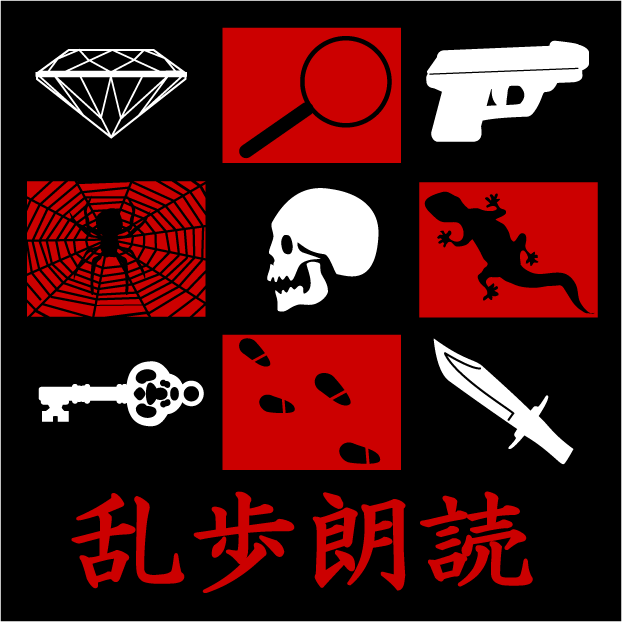top of page
鬼
1931(昭和6)年11月~
探偵小説家の殿村昌一は、その夏、郷里長野県のS村へ帰省していた。
S村は四方を山にとざされ、殆ど段畑ばかりで暮しを立てている様な、淋しい寒村であったが、その陰鬱な空気が、探偵小説家を喜ばせた。
平地に比べて、日中が半分程しかなかった。朝の間は、朝霧が立ちこめていて、お昼頃ちょっと日光がさしたかと思うと、もう夕方であった。
段畑が鋸型に喰い込んだ間々には、如何に勤勉なお百姓でも、どうにも切り開き様のない深い森が、千年の巨木が、ドス黒い触手みたいに這い出していた。
段畑と段畑が作っている溝の仲に、この太古の山村には似てもつかぬ、二本の鋼鉄の道が、奇怪な大蛇の様に、ウネウネと横たわっていた。日に八度、その鉄路を、地震を起して汽車が通り過ぎた。黒い機関車が勾配に喘いで、ボ、ボ、ボと恐ろしい煙を吐き出した。
山家の夏は早く過ぎて、その朝などはもう冷々とした秋の気が感じられた。都へ帰らなくてはならない。この陰鬱な山や森や段畑や鉄道線路とも又暫くお別れだ。青年探偵小説家は、二月余り通り慣れた村の細道を、一本の樹、一莖の草にも名残を惜みながら歩いていた。
朗読はこちらから!
江戸川乱歩 短編集(4)
二銭銅貨
双生児
疑惑
鬼
妻に失恋した男
bottom of page