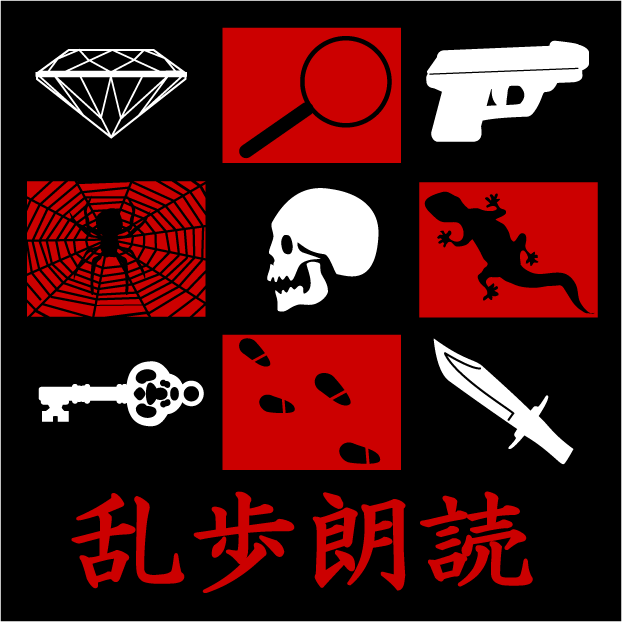top of page
火星の運河
「新青年」博文館、1926(大正15)年4月
又あすこへ来たなという、寒い様な魅力が私を戦かせた。にぶ色の暗が私の全世界を覆いつくしていた。恐らくは音も匂も、触覚さえもが私の体から蒸発してしまって、煉羊羹のこまやかに澱んだ色彩ばかりが、私のまわりを包んでいた。
頭の上には夕立雲の様に、まっくらに層をなした木の葉が、音もなく鎮り返って、そこからは巨大な黒褐色の樹幹が、滝をなして地上に降り注ぎ、観兵式の兵列の様に、目も遙に四方にうち続いて、末は奥知れぬ暗の仲に消えていた。
幾層の木の葉の暗のその上には、どの様なうららかな日が照っているか、或は、どの様な冷い風が吹きすさんでいるか、私には少しも分らなかった。ただ分っていることは、私が今、果てしも知らぬ大森林の下闇を、行方定めず歩き続けている、その単調な事実だけであった。歩いても歩いても、幾抱えの大木の幹を、次から次へと、迎え見送るばかりで景色は少しも変らなかった。足の下には、この森が出来て以来、幾百年の落葉が、湿気の充ちたクッションを為して、歩くたびに、ジクジクと、音を立てているに相違なかった。
朗読はこちらから!
bottom of page