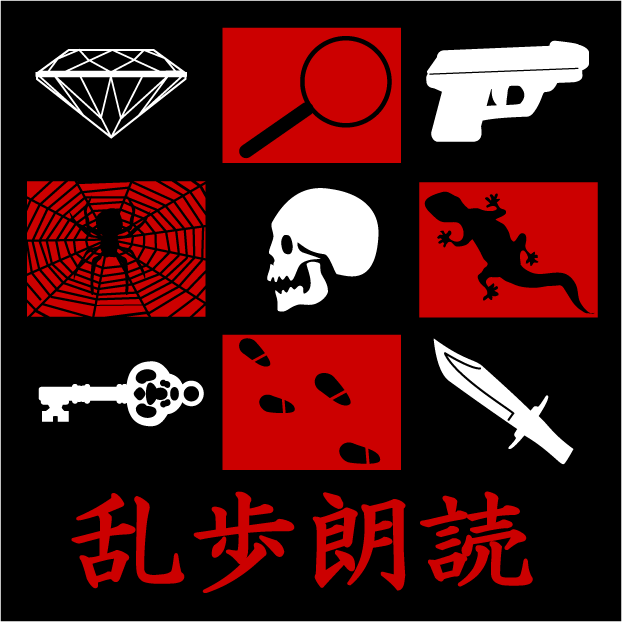top of page
一寸法師
「東京朝日新聞」朝日新聞社、1926(大正15)年12月8日~1927(昭和2)年2月20日
小林紋三はフラフラに酔っ払って安来節の御園館を出た。不思議な合唱が――舞台の娘たちの死物狂いの高調子と、それに呼応する見物席のみごとな怒号が――ワンワンと頭をしびらせ、小屋を出てしまっても、ちょうど船暈の感じで足許をフラフラさせた。その辺に軒を並べている夜店の屋台が、ドーッと彼の方へ押寄せて来るような気がした。彼は明るい大通をなるべく往来の人たちの顔を見ないように、あごを胸につけてトットと公園の方へ歩いた。もしその辺に友達が散歩していて、彼が安来節の定席からコソコソと出て来るところを見られでもしたら、と思うと気が気でなかった。ひとりでに歩調が早くなった。
半町も歩くと薄暗い公園の入口だった。そこの広い四辻を境にして人足はマバラになっていた。紋三は池の鉄柵のところに出ているおでん屋の赤い行燈で、腕時計を透して見た。もう十時だった。
「さて帰るかな、だが帰ったところで仕方がないな」
朗読はこちらから!
bottom of page